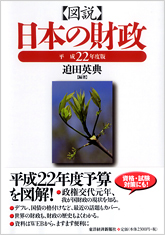図説 日本の財政(平成22年度版)
はしがき
本書は,財政の仕組みや現状について,図表を使いながら,できるだけ
具体的に分りやすく,また幅広く解説した本として,昭和30(1955)年に
はじめて刊行されて以来,多くの社会人や学生の方々に読み継がれてきま
したが,ここにその平成22(2010)年度版をお届けします.
このところの我が国経済・財政を顧みると,かつてない大きな変動が
次々と生じてきました.
一昨年秋のリーマン・ショック以降,我が国経済は急激な景気悪化に直
面し,政府は累次の経済対策により経済の下支えを図ってきました.景気
は,昨年春頃を底にようやく持ち直しの過程に入りましたが,この間昨年
夏の衆議院総選挙の結果,戦後初の本格的な政権交代となり,国の予算編
成は,その編成過程を含めて大きく変化することとなりました.また,最
近では,ギリシャの財政問題に端を発して,ユーロ圏を中心とする金融市
場が不安定化し,それが世界経済のリスク要因とされていますが,このこ
とを通じて,改めて日本の財政問題が注目され始めてもいます.
こうした状況を踏まえつつ,平成22(2010)年度版の編集にあたっては,
これまで同様豊富な図表によるわかりやすい説明を心がけました.また,
「コラム」を多数活用して,国内外を通じた最近の話題を含めて財政に関
する事項を説明するとともに,さまざまな経済政策全般についても目を配
り,編著者なりの視点から解説を試みています.
本書を読むに当たって,まず財政の仕組み,現状,制度に関する基礎知
識を身につけたいという方は,第1)部第1章,第3章,第2)部第1章,第2
章,そして第3章以降の「基礎知識」のところを読まれるとよいでしょう.
また,平成22年度予算の概要を知りたい方は,第2)部第2章の第2節及び
第3節や,第3章から第12章の各第3節などを読まれるとよいでしょう.そ
の他にも,本書では財政の理論や歴史,海外事例のほか,予算制度改革,
iv v
財政投融資,国庫金制度,税制改正,金融政策などについて解説していま
す.読者のみなさまの必要と時間にあわせた読み方をしていただければ幸
いです.
国の予算や財政問題と言うと,何か難しいもの,日々の生活と縁遠いも
のと思われがちかも知れませんが,決してそんなことはありません.
予算を使って国が種々のサービスを提供する際,その受益者は国民です
が,そのための元手も最終的には税金という形で国民が担うことになりま
す.元手がふんだんにあれば提供できるサービスも充実しますが,元手が
乏しければ提供できるサービスは限られます.元手が苦しいからといって,
安易に借金をして,それがどんどん膨らんでいってしまえば,将来に亘っ
て借金の返済に追われることになります.国の財政を巡る議論の本質は,
意外にもシンプルなものです.
どの程度の元手でどのようなサービスを享受するのか,また,その元手
を国民全体としてどのように担っていくのか,と考えることは,まさに国
民一人一人の今と将来の生活に直結するものであり,国民一人一人が真剣
に向き合うべき切実な課題と言えるでしょう.
本書が,この切実な課題に向き合うための一助となることを,筆者一同
心から願っております
資料編はWEBへ
http://www.toyokeizai.net/shop/books/download/nihonno_zaisei22/
商品を購入する
概要
目次
第1)部 財政についての基本問題 第1章 財政の役割と機能 1 財政とはなにか 2 財政の3機能 (1)資源配分の調整 (2)所得の再分配 (3)経済の安定化 第2章 財政をめぐる理論 1 財政学の歴史 (1)重商主義,官房学 (2)古典派財政学 (3)財政学の発展 (4)ケインズ理論 (5)現代の財政学 2 裁量的な経済政策をめぐる理論 (1)ケインズの考え方 (2)ケインズ経済学への批判 3 財政赤字に関する議論 (1)財政赤字の問題点 4 課税をめぐる議論 (1)基本原則 (2)租税体系 (3)課税の理論 第3章 財政の現状 1 財政の現状 (1)我が国財政の概況 (2)国民経済計算(SNA)における公的部門の状況 (3)財政赤字の国際比較 (4)これまでの財政状況 2 財政の課題 (1)概要 (2)国民の受益と負担(国民負担率)の動向 (3)財政健全化に向けた努力 コラム プライマリー・バランスとペイアズユーゴー(Pay-As-You-Go) 原則について 48 第2)部 財政の仕組みと関連する事項 第1 章 予算制度 1 予算制度 (1)財政と予算 (2)予算制度の概要 2 予算の編成・執行・決算 (1)予算の編成 (2)予算の審議と成立 (3)予算の執行 (4)決算 3 国の収入の概要 (1)租税 (2)その他収入 第2章 総説 1 平成21年度の経済財政運営 (1)平成21年度の経済情勢 (2)平成21年度予算の概要 (3)平成21年度補正予算(第1号)の概要 (4)平成21年度補正予算(第2号)の概要 2 平成22年度予算の編成 (1)国家戦略室及び行政刷新会議の設置と予算編成 (2)概算要求基準の廃止とマニフェストを踏まえた概算要求について (3)平成22年度予算編成の基本方針について (4)平成22年度予算の成立 3 平成22年度予算の概要 (1)ポイント (2)主要な経費 コラム 事業仕分けについて 第3章 社会保障 1 ポイント 2 基礎知識 (1)我が国社会保障の現状 (2)社会保障関係費の推移 (3)医療保険制度 (4)年金制度 (5)介護保険制度 (6)生活保護 (7)少子化対策 3 平成22年度社会保障関係予算 (1)概要 (2)年金医療介護保険給付費 (3)生活保護 (4)社会福祉 (5)保健衛生対策費 (6)雇用労災対策費 第4章 文教及び科学技術の振興 1 ポイント 2 基礎知識 (1)学校教育制度 (2)我が国の教育投資 (3)科学技術の振興 3 平成22年度文教及び科学振興関係予算 (1)概要 (2)義務教育費国庫負担金 (3)科学技術振興費 (4)文教施設費 (5)教育振興助成費 (6)育英事業費 4 平成22年度文化関係費 第5章 社会資本の整備 1 ポイント 2 基礎知識 (1)社会資本の定義 (2)公共事業の分類 (3)公共事業の推移 (4)公共事業の効率化・透明化の徹底 (5)社会資本整備の計画 3 平成22年度公共事業関係予算 (1)概要 (2)災害の予防と復旧 (3)道路,港湾,空港,鉄道(交通基盤)等 (4)住宅都市環境 (5)生活環境施設 (6)その他 第6章 経済協力 1 ポイント 2 基礎知識 (1)経済協力の諸形態 (2)政策的枠組み (3)ODAの現状 3 平成22年度予算における経済協力 (1)無償資金協力 (2)独立行政法人国際協力機構(JICA)運営費交付金 (3)留学生関係費 (4)国際機関への拠出 (5)円借款 第7章 防衛力の整備 1 ポイント 2 基礎知識 (1)我が国の防衛力整備の考え方 (2)現大綱の概要 3 平成22年度防衛関係予算 (1)歳出予算 (2)3分類 (3)主要装備品等とその他の物件費 (4)弾道ミサイル攻撃への対応 (5)SACO関係経費 (6)米軍再編(地元負担の軽減に資する措置)関係経費 (7)在日米軍駐留経費負担 第8章 中小企業施策の推進 1 ポイント 2 基礎知識 (1)中小企業政策の抜本的見直し (2)中小企業対策の体系 3 平成22年度中小企業対策予算 (1)概要 (2)株式会社日本政策金融公庫出資等 (3)中小企業の事業環境の整備 (4)中小企業の経営革新・創業促進 (5)政府系中小企業金融機関 (6)その他 第9章 農林水産業の振興 1 ポイント 2 基礎知識 (1)我が国の農林水産行政の推移 3 平成22年度農林水産関係予算 (1)概要 (2)施策の重点 (3)公共事業関係費 (4)食料安定供給関係費 (5)一般農政費 第10章 エネルギー・地球温暖化対策の推進 1 ポイント 2 基礎知識 (1)我が国の石油需給構造 (2)我が国の地球温暖化対策 3 平成22年度エネルギー対策予算 (1)概要 (2)燃料安定供給対策 (3)エネルギー需給構造高度化対策 (4)電源立地対策 (5)電源利用対策 (6)原子力対策 4 平成22年度地球温暖化対策予算 (1)概要 (2)分類ごとの解説 第11章 国債費 1 ポイント 2 基礎知識 (1)国債について (2)国債管理政策 (3)国債費 3 平成22年度国債費の概要 コラム 「資金の流れ」と国債管理政策 コラム 格付けについて 第12章 地方財政 1 ポイント 2 基礎知識 (1)地方公共団体の予算制度 (2)地方交付税制度の仕組み (3)地方分権改革の推移 (4)地域主権改革 (5)国と地方,地方団体間の比較 3 平成22年度地方財政計画 (1)概要 (2)主な歳出項目 (3)主な歳入項目 4 平成22年度地方財政対策 (1)概要 (2)主な措置 第13章 予算制度改革 1 ポイント 2 平成22年度における取組み (1)予算の組替え (2)特別会計の見直し 3 公会計の整備 (1)公会計充実の必要性 (2)公会計に関する取組み状況 第14章 財政投融資 1 ポイント 2 基礎知識 (1)財政投融資の仕組み (2)財政投融資の対象 (3)財政投融資改革 3 財政投融資計画の策定 4 平成22年度財政投融資計画について (1)平成22年度財政投融資計画の特色 (2)財政投融資特別会計積立金の一般会計への繰入れ 第15章 国庫金制度 1 国庫金制度 (1)国庫金 (2)国庫金の種類 (3)日本銀行の役割 (4)国庫余裕金の圧縮と繰替使用 (5)民間市場に対する配慮 2 財政資金対民間収支 (1)財政の執行状況の把握 (2)金融市場への影響の把握 第16章 税制改正 1 税制改正 (1)新たな政府税調の設置と平成22年度税制改正の経緯 (2)税制改革にあたっての基本的考え方 (3)新しい税制改正の仕組み (4)各主要課題の改革の方向性 (5)平成22年度税制改正の概要 2 関税改正 (1)関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案 第17章 金融政策 1 金融政策 (1)金融政策と金融政策決定会合 (2)金融市場調節方針 (3)金融調節 (4)日本銀行の自主性の尊重と政府との関係 2 金融政策の変遷 (1)量的緩和政策の導入・解除と政策金利の引上げ (2)平成20年秋以降の金融危機に対する日本銀行の対応 (3)政府のデフレ宣言(平成21年11月20日)後の日本銀行の対応 コラム デフレについて 第3)部 我が国財政のあゆみ 1 近代国家創設期の財政(明治元~ 22年) (1)明治維新と財政(明治元~ 14年) (2)松方財政と近代国家の体制整備(明治14 ~ 22年) 2 明治後半期の財政(明治23 ~大正3年) (1)日清戦争前後の財政(明治23 ~ 37年) (2)日露戦争前後の財政(明治37 ~大正3年) 3 大正から昭和初期の財政(大正3 ~昭和6年) (1)第1次世界大戦前後の財政(大正3 ~昭和2年) (2)金融恐慌と金解禁(昭和2 ~ 6年) 4 満州事変から終戦までの財政(昭和6 ~ 20年) (1)満州事変と高橋財政(昭和6 ~ 12年) (2)戦時財政(昭和12 ~ 20年) 5 高度成長・安定成長期の財政(昭和21 ~ 60年) (1)経済社会の復興と自立(昭和21 ~ 30年) (2)高度経済成長期(昭和30 ~ 45年) (3)経済構造の転換期(昭和45 ~ 50年) (4)安定成長期(昭和50 ~ 60年) 6 バブル経済以降の財政(昭和60年以降) (1)バブル経済の生成・崩壊とその後(昭和60 ~平成8年) (2)財政健全化への取組み(平成9年~ ) コラム 成長戦略について 第4)部 諸外国の財政 第1章 主要国の予算制度の国際比較 (1)予算の性格,対象 (2)予算過程 (3)各国予算制度の主な特徴 (4)財政規模の国際比較 コラム 主要国の経済対策について 第2章 アメリカ 1 財政政策の足取り (1)黄金の60年代(1961 ~ 69年) (2)インフレ抑制の試み(1969 ~ 80年) (3)レーガノミックス(1981 ~ 88年) (4)長期景気拡大下における財政収支の黒字化(1989 ~ 2000年) (5)ブッシュ政権の経済政策と財政収支の赤字化(2001年~ 08年) (6)オバマ政権における政策 2 2011年度予算教書の背景と概要 (1)最近の経済情勢(2001 ~ 08年) (2)2009年の経済情勢 (3)2011年度予算教書における経済見通し (4)2011年度予算教書の特色 (5)2011年度予算教書の歳出入,財政収支 3 景気対策法の進捗状況 第3章 イギリス 1 財政政策の足取り (1)サッチャー政権下(1979年5月~ 90年11月)及び メージャー政権下(1990年11月~ 97年5月)の財政政策 (2)ブレア政権下の財政政策(1997年5月~ 2007年6月) 2 2010年度予算案の背景と概要 (1)2010年度予算案の背景 (2)旧労働党政権が3月に発表した2010年度予算案の概要 (3)新政権による2010年度歳出削減と緊急予算の概要 第4章 ドイツ 1 財政政策の足取り (1)旧西ドイツ経済の復興と発展(1945 ~ 67年) (2)財政政策の登場(1967 ~ 78年) (3)積極的財政政策の失敗と財政再建への取組み(1978 ~ 90年) (4)ドイツ統一による財政赤字拡大(1990 ~ 98年) (5)シュレーダー政権の財政政策(1998 ~ 2005年) (6)メルケル政権の財政政策(2005年11月~ ) (7)ドイツの財政赤字をめぐる動き (8)景気刺激策の概要と財政健全化の取組み 2 2010年度予算の背景と概要 (1)2010年度予算の背景 (2)2010年度予算の概要 第5章 フランス 1 財政政策の足取り (1)ミッテラン政権下の財政政策(1981 ~ 94年) (2)シラク政権下の財政政策(1995 ~ 2007年) (3)サルコジ政権下の財政政策(2007年~ ) 2 2010年度予算の背景と概要 (1)2010年度予算の背景~最近の経済情勢と見通し (2)2010年度予算の概要 コラム ギリシャ財政問題とEUの財政規律 第6章 中国 1 予算制度 (1)制度の概要 (2)予算編成過程 (3)決算 (4)歳入及び歳出 (5)転移支付制度 2 財政制度の足取り (1)計画経済時代の中国財政 (2)財政請負制度─改革開放から分税制開始前まで (3)分税制改革─1994年 (4)企業所得税・個人所得税の共有税化─2002年 (5)農業税の廃止─2006年 (6)企業所得税率の原則統一─2007年 3 2010年度予算の背景と概要 (1)最近の経済情勢 (2)2010年度の中央と地方の予算状況